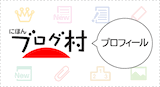伝達と齟齬 〜または独善的な伝達者
次に考えられることは伝える人と伝えられる人との齟齬です。これは伝える人と伝えられる人とするよりも、教える人と教えられる人と捉えた方がわかりやすいかもしれません。つまり先生と生徒ですね。

先生が生徒になにかを教える場合
先生がなにか教えようとしています。なににしましょう。国語とでもしておきましょうか。それを生徒に教えるとなると、その関係は教師Tが国語という内容Aを、生徒Sに伝えるのだからTA→SAとなります。
【高校生のための批評入門】
(様々な人の批評やエッセイが並べられていて読んでてとても面白い。私が読んだのは単行本版。拾い読みだけしました)
この時Aはその中に123456789と含まれる、ととりあえずここでは仮定してみます。すると図はTA(123456789)→SA(123456789)となるわけです。しかし普通、先生の言ってることなんて聞いただけですべてわかるわけではありませんね。となるとこの123456789において伝達が完璧ではないということになります。
1.生徒が歯抜けに受け取っている
まず教師がTA(123456789)を伝えようとしたとして、生徒の側ではSA(1 45 89)としか受け取れなかったとします。すると残り2367が伝達不足ということになります。これが伝達の齟齬となる基本的な問題でしょう。
2.教師が不十分にしか伝えていないが、自覚がない
次に教師Tは自分の伝達内容において123456789を伝えたと自負しているとします。しかし生徒Sの側では14589しか伝達されていないわけです。二人の間に123456789がちゃんと共有できていれば伝達は成功ですが、それが成り立っていなければ失敗していることになります。このことに気づいていなければ、伝達者である教師Tは自分が伝えたと自覚している以上、相手の理解が足りない、と受け取るだけです。となると生徒Sを理解力が不足している、というだけですましてしまい、お互いの齟齬は埋められません。こうして伝達の齟齬は放っておかれることになります。そのまま固定化されてしまうわけですね。

態度としての伝達問題
ここで問題となってくるのは、伝えるべき内容である123456789自体が問題ではなくなってしまったことです。そうではなく、T→Sという関係自体が齟齬の原因となってしまっているからです。
どういうことでしょう。
まずTは自分ではA(123456789)を伝えた、と自負しています。ですからSがA(123456789)と理解せずA(1 45 89)としか理解しないのは相手に問題があると捉えています。そして相手に問題があると仮定してしまうことによって、自分の伝えたA(123456789)を完全であるとも仮定してしまっています。
しかしもしかしたら教師Tが伝えた内容自体がA(1 45 89)であった可能性もあります。その場合TA(1 45 89)→SA(1 45 89)となり生徒側の理解は完璧です。なんの問題もないことになりますが、相手に問題ありと仮定してしまうことによって自分の伝達内容を棚上げにして本来伝えるべき内容であったA(123456789)を前提とし伝達に齟齬があるように捉えてしまいます。実際に伝えたA(1 45 89)は生徒側でもA(1 45 89)と問題がないにも関わらずです。
伝達者による自己の伝達内容の絶対視という齟齬
つまりこの場合、伝達者は自分の伝達内容を絶対視してしまい、独善的な伝達者になってしまっているのです。その結果お互いの間に生じた齟齬を相手の問題とし、伝達の内容、過程において十分な方法がとられたか、ということが、無視されてしまいます。

まとめの図解
これを避けるためにはどうしたらいいでしょうか。まとめてみましょうね。
1.伝達者は自らの伝達内容を過不足のないものであるか検証しながら伝達する必要がある
TA(123456789)
を
T
↓ 要検証
A(123456789)
としなければならない
2.伝達される側の理解が、自分の伝達した内容においてどの程度理解されたかを検証しながら伝達する必要がある
TA(123456789)
↓
SA(1 45 89)の場合
↓
A( 23 67 )が欠けている
まぁ、こんな感じでしょうか。
しかし相手の理解が実際足りないということもありえます。今度はそのことについて考えてみましょうか。
次の日の内容
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/05/29/153035
前の日の内容
難解な思想/内容が難しい理由と伝播の仕組み ~無数の要素と膨大な量と他者との齟齬 - 日々是〆〆吟味
お話その19(No.0019)