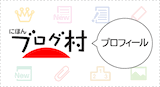伝える側の拒絶の問題 〜謙虚によく知ろう、かな
相手への拒絶と伝達の齟齬
伝達の齟齬が生じる問題は、まず互いに相手の伝達内容に対して拒絶的であるからだ、と、とりあえず考えられました。

これはごくごく当たり前のことでしょうから、すぐ納得がいきそうです。言う方も聞く方も、相手を受け入れる気がなければ話が通じなくても普通でしょうね。
さて、ではお互いに相手のことを受け入れる態度がある、と仮定しましょう。ですが、この受け入れる態度というものもどのようなことを指すのか、これを少し考えてみましょうか。
伝達者側の受け入れる態度

まず伝達者の側です。
1つは自説に固執しない、ということでしょう。
自分が伝えようとする内容を間違いないものとして疑わない。また自分の伝えようとしている内容は正しいので、それが伝えられて理解されないのは相手に問題がある。こうした態度を捨てることですね。
2つめとして、相手の理解程度がどの程度かちゃんと把握できるかどうかが重要になりそうです。
伝達がU1A(123456789)→U2(1 45 89)であったとして、U1がU2の理解程度を1 45 89であると正確に把握していないと、どこを理解していてどこがわからないのか不明なままです。そのため再度伝え直そうとしても、どこを重視して相手に伝えればいいのもわからないままとなっています。
下手をすれば理解できる部分だけを伝えて、肝心のわかっていない部分を補足説明しないままに終わってしまうかもしれません。こうなると、相手側が理解を増すことはありませんね。そして伝達者側でもいくら説明しても理解しないやつだ、と相手を決めつけてしまう可能性もあります。
3つめとして、自分の伝えようとしている内容をよく知っている必要かあるでしょう。
当たり前かもしれませんが、自分の伝えようとしている内容をよく知らないままに相手に伝えようとしても、過不足なく相手が理解してくれるとは限りません。もしかしたらU1A(123456789)→U2と自分では思っていても、実際はU1A(1 45 89)→U2であるかもしれず、先日も考えたようにこの場合U2A(1 45 89)となれば理解力は完璧です。しかし伝達者の方が自分の伝達内容をA(123456789)であると自覚してしまえば、相手の理解力に問題があることになってしまいます。出来の悪い教師や上司にありえそうな話ですね。
また2つめとも重なってきますが、こうした伝達者側の理解が十分でなければ、相手の理解がどの程度に達しているのかも判断できません。U1A(123456789)を熟知しているからこそ、相手の理解がU2A(1 45 89)であることを把握できるのです。そのため相手の問題を正確に判断するためには、こちら側がよく知っていなければならないことになります。
【サックス,シェグロフ,ジェファソン『会話分析基本論集』】
(こんな本もある。持ってるけどまだ読んでない。いつ読めるかなぁ)
続いて受け入れる側の問題について考えていきたいのですが、ちょっと長くなってしまいました。また翌日へと持ち越すことにしたいと思います。
次の日の内容
情報を伝播された受け入れる側の信用問題 ~相手を信じることができれば話を聞く - 日々是〆〆吟味
前の日の内容
聞く態度と伝播の齟齬 〜会話を苦手とする能力以前のコミュニケーションという問題 - 日々是〆〆吟味
お話その22(No.0022)