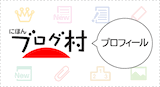前回のお話
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/12/04/190003
政治的保守と経済的覇権主義 〜大きな経済は守るが、歴史や文化や小さな経済の生活者は守らない?
保守の立場 〜自らで明確化、歴史的文化
保守の立場が難しく自らで守るべきものを明確にしなければならないのと同時に、日本であれば日本の伝統や文化を踏まえていることが重要である、と前回お話してみました。これは日本という範囲での歴史ですね。
今の政治的保守とは
そこで今の保守政治というものがどこまで保守なのか、ちょっとよくわからなくなります。というのも本来保守というものが見ている歴史の射程は平安時代くらいから続くものであって、かなり長いものです。それに比べると今の政治主導している保守というのは高度経済成長からバブルくらいの歴史を範囲として考えている、と小林よしのりですら述べていたことがあります。当然本来の保守からすれば近視眼的すぎるわけですね。保守の持つ恣意性がここで問題になっているわけです。
経済第一主義の保守 〜もしくは経済的覇権主義

そのため今の政治的保守というのは高度経済成長からバブルを保守するのであり、経済第一主義の保守と言えるわけですね。こうした経済成長ががむしゃらな戦後復興にあったことは確かですが、もう一つ戦前からの目的を違う形で果たした側面もあります。すなわち覇権国家としてかつてのヨーロッパ諸国のように植民地をたくさん持ってる大国になることです。ですがこれは敗戦と共に挫折してしまいました。その代わりとして経済では負けないぞ、と一時期はアメリカを越して世界一になりました。ふた昔は今の中国のような位置に日本はいたわけですね。
経済第一主義にとっての歴史や文化 〜非効率な金にならないもの
そんなわけで高度経済成長からバブルを保守するというのは、ある意味では政治的な覇権国家として挫折したが経済的には世界制覇した、すなわち経済的覇権国家としての日本を保守するという意味でもあるかもしれません。となると日本の歴史はどうなるのか。多分そんなことは考えていないのだと思います。というのも経済効率をよくするためにはそんなもの踏まえていたら非効率だからですね。ですから歴史的な観点を重視する保守とは本来相入れないはずなのです。

たとえば大阪ではなんばのど真ん中に廃校になった小学校が残されていました。地元の人々にとって思い出の残る大切なものであり、かつての大阪商人たちが寄付によって建てた建築としても由緒ある価値のあるものでした。そのため一等地であるにも関わらず長年放置され開発されていませんでした。しかしそんなもの無駄だと今では潰されて複合商業施設が建っています。この場合地元の人が残して欲しいもの(伝統/文化)を経済第一主義で切り捨てたわけです。
経済第一主義が保守の理由 〜国民の生活を守るためには経済を守る
ではなぜ経済第一主義が保守なのかといえば、国民生活を豊かにするためには経済が良くないと成り立たないからです。つまり国民の生活を守るために経済を重視している、というわけですね。これは敗戦後のような窮乏期には当然の考え方でしょう。松下幸之助の水道哲学とも一脈通じそうな態度ですよね。
大きな経済を守る
しかし今は物の足りない生産中心の経済システムの中にいません。消費中心の経済です。となるとイノベーションによって新しい商品を生み出してもらわないと経済も活性化しません。そのためイノベーションを起こしてくれそうな大きな会社にばかり援助します。いわゆるGAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)みたいな会社が起これば消費圏自体が生まれてくるようなことになるのでその経済的影響は甚大です。
小さな経済は切り捨てられる
ですがここで福田恆存の保守の考え方を思い出してみましょう。保守とは横丁のそば屋を守ることである。こういうものでしたね。しかし横丁のそば屋は個人経営の小さな店舗です。それは町の常連には愛されているかもしれませんが、経済圏を生み出すことはしません。そのため経済第一主義の考えではそんなもの守りません。イオンやガストやセブンイレブンに潰されるのがオチです。国民生活を守るはずの経済第一主義の保守が、生活者を押し潰す方に協力しているわけです。
消費社会にも関わらず生産中心思考?
しかも既に消費中心の経済であるにも関わらず、どうも生産中心の経済の考え方から抜けてないのかもしれません。先の学校だって観光資源として使ってもいいはずですが、商業施設を選んでしまいます。物を売る方が重視されるわけですね。ですが以前見たように消費社会は既にある物を差異化することによって新しい価値を生み出すことにあります。あるものはなんでもいいのです。使い方次第です。それなのに人を呼ぶのに商業施設といったハコモノを作ったり、イベントを開いたりとなにか新しく手を出してしまいます。考え方まで高度経済成長のままなのかもしれません。しかし今はそんな景気のいい時代ではありません。きっとあるもの使うより新しく作ったりやったりする方がお金かかるんじゃないでしょうか。
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/09/170029
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/10/170055
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/11/170027
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/28/120012
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/29/120049
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/10/30/120038

大きな経済を守って零れ落ちてゆくものたち
そんなわけで経済第一主義の保守は歴史や伝統や文化を守ってくれません。守ってくれるのは経済だけです。それも大型の経済だけを守ってしまうので、小さな経済で生きている人は守ってくれません。結果、得る者は得て、得られぬ者は得られぬ、といったことになって格差が生じてしまっているのかもしれませんね。でもそれを国民は支持しているとみなされるので、これを日本の考えだと国内外共に理解するしかないのでした。
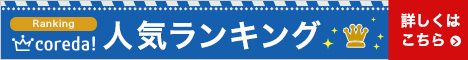

欠乏した自力と野心の経済的覇権主義
そこでもうひとつやっかいなのは、経済第一主義、いえむしろ経済的覇権主義なのかもしれませんが、どうも自力で世界一の経済大国になろうと野心を持っているのではなく、大国にくっついて一緒に金持ちになろう、といった姿勢のようにも見えてしまう気がすることです。ある評論家が自虐史観からの脱却って、ジャイアン史観からのび太史観に変わっただけで、いじめっ子(侵略)だったのがいじめられっ子(東アジア諸国での孤立)に気分が変わっただけじゃん、そしてアメリカをドラえもんにしてる、なんて言ってた気がしますが、案外スネ夫(ゴバンザメ)なのかもしれませんね。それなのに日本は偉い、と言っているのはちょっと二枚舌もいいとこな気もします。せめて政府に逆らった前川喜平元文科事務次官みたいに面従腹背で、いざとなったらいいとこ掴んでアメリカ出し抜くくらいのこと考えて牙でも磨いておいて欲しいですけどね。もしくは黒田如水が関ヶ原の決戦のあと、家康に右手をとって褒められた、といって喜んだ子の長政に対し、その間左手をどうしていた(その間に刺せ)、といった気概でしょうか。今なら如水じゃなくて長政になるかもしれませんね。江藤淳なんてアメリカに逆らえないそんな日本を嫌いで批判していたはずですが、今そんなこと言ったら、日本でていけ、って言われちゃうんで保守とはなんぞやというのは大切な問題なのかもしれません。
次回のお話
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/12/06/190050
気になったら読んで欲しい本
福田恆存『保守とは何か』
私は読んでないんですが、生活者からの保守という観点はやはり福田恆存に依るのが一番いいかと思います。
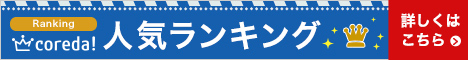
江藤淳『成熟と喪失』
江藤淳は戦後の日本がアメリカ化していくことによっていかに多くのものを失ってきたのか、ということを同時代の日本文学の中に探って批評にしました。それがこの本です。江藤淳の立場も自分のノスタルジックな過去を理想化していると批判もされますが、アメリカ化をグローバル化として捉えれば今となんら変わりませんので、案外今の方が切実感を持って読まれるかもしれません。もしくはこうしたアメリカ化の屈託が一切なくなってしまったからこそ、経済第一主義が保守でありえるのかもしれませんね。
次回の内容
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/12/06/190050
前回の内容
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/12/04/190003
 にほんブログ村
にほんブログ村
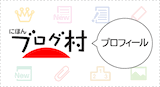
お話その140(No.0140)