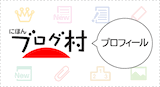前回のお話
https://www.waka-rukana.com/entry/2020/02/04/200016
庶民から大衆への変化と情報社会 〜メディアが当たり前になって庶民は大衆になった?
あまりに大衆のお話が陰気になってしまいますので、中島岳志の解釈を添えて大衆に対置する選ばれた少数者(貴族/エリート)=庶民という考え方を持ってきてみました。これはほっと安心するお話でもありますが、こうした庶民と大衆の移動(変化?)みたいなお話を、ちょっと私なりに読んだ話から勝手に理解したものをまとめてちょっぴり書いてみたいと思います。
【100分de名著 オルテガ『大衆の反逆』】
大衆の原像=自足自律した生活様式=庶民?
昔、吉本隆明が自分の立場を鮮明にするために大衆の原像という考え方を出したのですが、それはどんな状況でも一定の生活様式を継続させ続ける人たちのことを指しているようです(よくわからない)。戦争で負けた時も、衝撃を受けるよりもそのまま同じようにして一日の生活を行なっていた、ということが例にも出されたそうです。

こうした大衆の原像と呼ばれた生活様式があるとして、それを同時に庶民と呼んでしまうことは正しいのかどうかはわかりません。しかし自分たちの生活圏内において自足自律し、それを超えたところにある問題を切り離す代わりに首もつっこまない、という点はどちらも同じような特徴がある、とここでは考えてみましょう。無理して吉本的大衆の原像の特徴を庶民にも当てはまると考えてみるわけですね(そして一旦中島岳志的な大衆像を棚に上げる)。
これは大勢に左右されないという点でいいことかもしれませんが、同時に生活の中で実感のわかないものは理解しないということでもあるかもしれません。そのため社会や政治的な問題にも無関心(というか切り離されている?)になってしまうかもしれませんから、民主主義社会では問題でもありますね。
庶民の転向と情報化社会
そうした庶民の姿が80年代頃から変わってきたのではないか、と、当時の対談で柄谷行人が発言していたことがありました。大衆の原像といって、同じ生活様式を続ける人たちを吉本隆明は自分の思想的基盤として考えているけど、その大衆自体が転向してしまったらどうするのか。つまり、かつての大衆の原像=庶民は自足自律していたかもしれないけど、80年代になって情報化社会になったら、メディアによって伝えられてくる情報に対して庶民だったはずの人たちが平気で意見をするようになった、それは庶民としての自足自律からメディア空間にふらふらと漂うだけの大衆になったのではないか、つまり大衆の原像たる庶民は大衆へと転向してしまったのではないか、と言うわけですね(私の勝手な解釈かもしれない)。

柄谷行人は昔ならTVのレポーターが街頭インタビューで社会問題について尋ねても、いや、自分はわからないから、といって顔を赤らめ逃げていたのが、今はどこで聞いたのかもわからないようないっぱしの意見を我が事のように言うようになった、とも言っていたかと思います。同じことは最近(2014年)になっても呉智英が次のように言っていました。
近代以前の場合、俺は「民衆」と区別しているけれども、当時の民衆は節操みたいなものがあった。それを全面的に信頼していいかどうかは疑問だけど、やはり庶民が培っていた行動規範みたいなものはたしかにあったと思う。
ネットは、昔の村落共同体が生きていたときの井戸端会議とは違うんだ。昭和30年頃、当時はラジオだったんだけど、ラジオのアナウンサーというかレポーターが録音機をもって井戸端会議に行くと、みんな照れて話さないんだよ。それで録音機がなくなると、またみんなワイワイガヤガヤやる。自分の言説の意味がわかっているんだ。
呉智英 × 適菜収 【第5回】「保守も革新も、右翼も左翼も問題は知性の欠如」() | 現代ビジネス | 講談社(3/6)
(ちなみに呉智英は吉本隆明を評価しませんし、柄谷行人たちポストモダン思想も当時の左派の衣替え程度にしか評価していません。立場が違っても同じような認識をしているわけですね)
【柄谷行人『ダイアローグ』】
(柄谷行人の対談集なんですが、どの巻で話されていたか忘れてしまいました。80年代でしたから、このどちらかだと思います)
これは、マスメディアが大きく発展することによって、人々の意識が庶民から大衆へと変わっていったことを意味するのかもしれません。TVでもネットでも、その情報の届く範囲は莫大です。そしてまた、こうしたメディアの影響の中でしか暮らしていけないほどに私たちの生活はメディアに浸されていると考えることも出来ます。
大衆と情報化社会
それはある意味では当たり前のことなのかもしれません。大衆はMassesの訳語で、マスメディアやマスコミのマスは大衆のことだからです。つまりたとえ自足自律した庶民であったとしても、高度に情報化社会へと変化した現代にあってはマス(大衆)メディア、マス(大衆)コミュニケーションに組み込まれた上でしか自足自律出来なくなります。もしそうした大衆現象から逃れたければ、ほぼ一切のメディアから離れなければなりません。そんなことをすれば自足自律の庶民としての在り方からも離れてしまうほどに、マスメディア/マスコミュニケーションは日常化しています。

そして近代において大衆が生まれてきた理由にも、もしかしたら出版によるマスメディアの誕生、すなわち新聞による面もあるのかもしれません(よく知らない)。
こうして社会が情報化社会へと変貌するに従って、自足自律していた(と思われた、もしくは期待された)庶民も大衆へと変化していったのかもしれませんね。
【オルテガ『大衆の反逆』】
次回のお話
https://www.waka-rukana.com/entry/2020/02/11/200010
お話その172(No.0172)