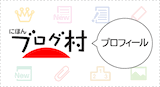前回のお話
世界の広がりと情報化社会と大衆 〜広がった世界と情報化社会の中の大衆と〝私〟
庶民と大衆の対比をもう一度私なりに考えてみましたが、とりあえず大衆が情報化社会の中の存在であると仮定してみましょう。もし今の世が民主主義的社会ではなく、社会的な決定が大半の人を預かり知らぬところで決まっているとしたら(そしてその影響がそうした人々に訪れないのなら)、今でも庶民はそのまま生きていたかもしれません。それが不可能になったのは私たちの世界が村落共同体のように狭く、隅から隅まで知り尽くしているようなものではなく、むしろその大半を未知のままでしか把握せざるを得ない世界に生きているからだと思います。そのため世界についての知識=情報はメディアを通してしか不可能であり、また技術の発展と共に情報・交通も拡大し、必要かつ伝達可能な領域が爆発的に増えたからだと考えられる気がします。すなわち私たちは自分たちの生きている世界の姿はメディアを通してしか把握できなくなってしまったのでした。

マスメディア・マスコミュニケーションの中で生きる私たち
そしてこうした拡大した世界の情報を伝えるものがマスメディア・マスコミュニケーションということになります。そしてこのマスは大衆のことを意味します。となれば、私たちはこうしたマスメディア・マスコミュニケーションによって伝えられる情報社会に生まれ育って生きていく以上、大衆としての生から逃れられないことになります。言い方を変えると、常にマスメディア・マスコミュニケーションにさらされ続けることによって、世界のひとりひとりが大衆として規定されている、と理解することも出来ます。
【マクルーハン『メディア論』】

大衆として規定されていく私たち
大衆がオルテガ的なものであるのかは、実際のところわからないのかもしれません。科学的/実証的に定める方法はどうしたらいいのか、少なくとも私にはわかりません。ただ思想的/哲学的にオルテガの言ったことは嫌々でも納得させられてしまうところがあります。そしてもしマスメディアやマスコミュニケーションによって流される情報が、無自覚/無意識のうえでもオルテガ的な大衆を想定しているのだとすれば、私たちはやはり大衆となるように規定され続けているようにも思えてきます。
【オルテガ『大衆の反逆』】
大衆と大衆以外への自己規定の軋轢
そうなると、私たちはいかにして大衆として型にはめられながら、同時に大衆にならずにすませるにはどうするか、という難しい問題に追い込まれていくことになります。大衆というだけでも困った問題なのに、それを他人事としてではなく我が事としてしか迫ってこないとすれば、もひとつ問題が難しくなっていくような気がしますね。

次回のお話
https://www.waka-rukana.com/entry/2020/02/14/200010
お話その173(No.0173)