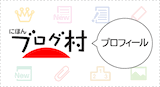言葉の規則と文化の規則 〜人間と他者、っていう規則ですね
言葉と人間
言葉というものが人間の基本的な能力であることは疑えないと思います。アリストテレスは人間だけが言葉をもっている動物(大意)だと述べていますし、哲学的には大昔からそう捉えられている年季の入った考え方と言えそうですね。
https://www.andrew.ac.jp/soken/pdf_3-1/sokenk173-1.pdf
(3ページめの冒頭に引用があります)

そして言葉が意味を持つことは、そこに複雑な内容を表現することが可能な規則があるからだと考えてみました。言葉の要素としては音であり、それは色や身振りとも変わらぬ一つの要素でしかないのですが、それがなぜ音のみが言葉となれたかといえばそこに規則があるからだ、というふうに考えました。そしてなぜ音が規則を有する言葉になり得たかといえば、単に人体の器官の中で最も労力なく発せられるのが口と舌だったからだ、というわけです。一番楽だったから複雑に意味構成していく規則を発展させることが出来たわけですね。
他者と規則
ここで他者について思い返してみましょう。
他者とは同じ規則を持たない人間のことを指しましたね。先日日本人とアメリカ人とでは謝罪の意味が違うと書きましたが、同じ行為でも意味するものが違うから、日本人とアメリカ人は違う規則を持つ他者だ、と考えてみました。
https://www.waka-rukana.com/entry/2019/06/04/153050

ここでは確かに日本人とアメリカ人は他者といえそうです。なにせ一緒に頑張ろうと謝るのと謝ったから責任を追及していいと思う間柄ではコミュニケーションはうまくいきません。文化的背景により同じ行為でも意味が違うのですから話が通じなくったって仕方ありません。
言葉の規則の違いと文化の規則の違い
しかし、言葉ということで考えてみますと、この規則の違いというものも少し変わってきます。確かに日本人とアメリカ人では行為の意味が違います。それは文化的背景によるもので、いってみれば後天的に学習された規則が違うわけです。

それに比べ言葉の規則というものは日本人もアメリカ人も人間である以上共通して持っているはずです。すなわち文化的規則は違うけど言語的規則は共通して持っているはずです。それは日本語と英語という形で異なっていますが、自分たちが理解したかったり伝えたかったり説明したりするものとしての言葉の規則は互いに持っているわけです。
ここから他者同士のコミュニケーションの可能性が開かれてきそうですね。
参考となる本
【アリストテレス『政治学』】
動物たちのなかで言葉をもっているのは人間だけである
はアリストテレスの『政治学』にあるそうです。岩波文庫なら手に入りやすいだろう、と思っていたら品切れの様子。新品で手に入るのは西洋古典叢書かアリストテレス全集の中の一冊だけみたいです。たまたま今増刷されてないのかもしれませんね。学術書はなかなか増刷しませんからね。
次の日の内容
論理的意味としての言葉の規則 ~コミュニケーション能力を支える言葉の原理 - 日々是〆〆吟味
前の日の内容
権力と言葉の相互関係 ~命令と言葉の規則による論理 - 日々是〆〆吟味
お話その32(No.0032)