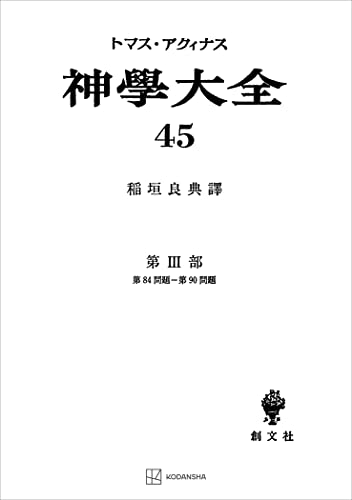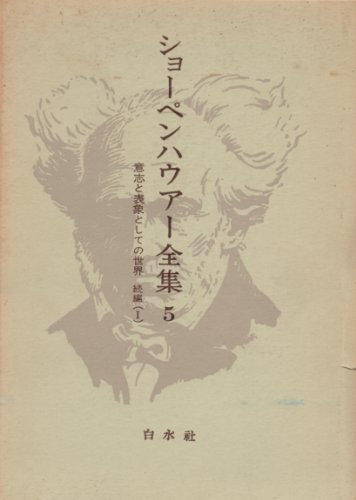初心者向けのリストは以前に書いたものがこちらにあります。最初に哲学書を読もうと思われたら下記のリストのほうがいいかもしれません。
最難解な哲学書 30冊
以前難しい哲学書の中から初心者の人でも読めそうなものを選んだことがありました。それが適切かどうかは納得されるかわかりませんが、少なくとも短かったり拾い読み出来るということを主眼にしたものを並べてみました。
しかし哲学書というとそうはいかないものがたくさんあります。なんならそうではないものの方が圧倒的に多いかと思います。なにせ哲学というものはよくわからず難しいと思われているものの代表的なもののひとつです(多分)。読みやすいものの方が珍しいのは仕方ないかもしれません。
そこで今回は逆にとびきり難しいだろう、と思われる哲学書の類を選んでみました。もし初心者むけとみなしたものを読んでみて、飽きたらなくなって他にも読みたい、と思われる方がいらっしゃいましたら、ここから選んでみるのもいいかもしれません。またそんな簡単なものなんて読んでも哲学じゃないぜ、と思われる方もいるかもしれません。そうした方々にはとても難しいと思われる哲学のイメージぴったりのものかもしれませんので、並びだけでも見てみてくだされば楽しんでもらえるかもしれません。
また簡単な哲学や哲学者/哲学書、哲学史の紹介にもなっているかもしれませんので、ざっと知るくらいの役にもたつかもしれません(たつといいなぁ)。
選んでいるうちにかなりの数になってしまいました。そのため文量も相当のもの(2万字ほど)になってしまいましたので、お時間のある時にでもまた来て眺めてみてください。
選ぶ基準
とりあえずとても難しい哲学書を選ぶといってもある程度の基準を持ちたいと思います。
1.歴史的評価の高いもの
まずは哲学史に出てくるような有名な本を選ぶことにしたいと思います。中にはとても難しくて現代の古典とみなされている本もあるかと思いますが、ここではオーソドックスな哲学史にあらわれる哲学書を選びたいと思っています。
簡単に歴史的にいえば、ソクラテスからハイデガーくらいを順番に並べてみようかと思います。こうした哲学的名著は間違いなく歴史の評価に耐えた、人類の最古典であることは間違いありません。そのためそこに書かれていることが難しくとも、無意味であったり無価値であったりするということはまずないと考えていいでしょう。
ただ逆に私たちの日常の世界と歴史も文化も隔たっている著作たちですので、そうした時間/空間的な壁があってわからない、より難しいということはあります。哲学は主にヨーロッパのものですから文化圏はヨーロッパですが、中世や古代、ギリシャやローマ、近代ドイツなどと地域は似ていても文化自体がまるで違うということはいくらでもあります。そのため読者である私たちにとって知らない文化圏であればあるほどわからなくなり、また基本的に時代が古くなればなるほど接点が少なくなって難しくなるかもしれません。
そういうわけで並び順は古いものから新しいものへとします。ですが厳密に時代順というわけでもなく、大体の時代区分でわけられているとお考えください。
2.分厚いものや巻数の多いもの
初心者むけ、とした時には出来るだけ薄いものを選んだのですが、今回は最難解本ですので逆にとにかく分厚いものを選ぶことにしました。
そのため版によっては何冊も分冊されているものもあります。あまりに長い巻数のものは最初と最後の巻のみリンクを載せておくことにしました。
3.翻訳も難しいとされているもの
これは私が知っているものだけになりますが、同じ本でも複数の翻訳がある場合、読みやすかったり難しかったりという評判があるものもあります。そこで最難解ですので、より難しいとされているものを選んでみることにしました。
ただ翻訳は次々出てくる場合もありますので、私には当然把握しきれません。そのため完全な判断などては到底ないということをご了承ください。
4.西洋哲学の範囲内のもの
哲学書といっても洋の東西まで広げると収集がつかなくなってしまいます。そのためいわゆる哲学とみなされる西洋哲学に限って選んでみたいと思います。
5.哲学以外の本も若干含まれる
ただ、哲学書ではないんだけど難しくて分厚かったりする本も選んでいます。というのも哲学といっても狭義の哲学だけが西洋哲学ではなく、キリスト教やイスラーム哲学の関係もあるからです。
特に中世はヨーロッパはキリスト教の世界ですからキリスト教を無視しては成り立ちませんし、思想的にもギリシア哲学を継いだのはアラブ世界でした。これらキリスト教・イスラーム哲学はギリシア哲学を引き継いでいることは間違いなく、哲学というよりも神学なんだけど、やっぱり哲学の内にも含められることが往々にしてあります。
ただ今回は私の限界もあってイスラーム哲学は選んでおりません。他にも哲学とも宗教とも関係ないけど分厚いから選んだものなどもあります。ちょっとこのあたりはいいかげんです。
また紹介する本の中には、私の限界から読んでいないものも含まれています。ものによっては手に入りにくいものもあります。Amazon等で値段を見るとどれくらい稀覯本なのかわかります。とても有名なものは大体岩波文庫や世界の名著に入っているんですけど、ちょっと変わっていて単行本でしか出ていないものなどはびっくりするような値段になっているものもあります。興味ありましたら覗いてみてください。
説明も私の限界があってまちまちなものになっていますが、興味を持ってもってもらえるよう努力はしたつもりでいます。ただいいかげんな説明を免れていないでしょうから、本格的に詳しいことは解説書等によって理解していただければ幸いです。
古代 8選
ギリシア 3冊

ギリシア以前にも哲学と呼べるようないとなみはあったと思われるのですが、記録されて我々に伝えられた哲学はギリシアからになります。これは記された歴史が主にギリシア以降ということに関わってくるのだと思いますが、非常に高い水準のギリシア哲学(もしくは文明)がいきなり現れたとは考えにくいらしく(ギリシアの奇跡としてそう考えられていた時期もあったらしい)、それ以前にもエジプトやバビロニアなどで高度に発展した文化思想が影響しているそうです。ただそうしたギリシア以前の思想はあまり残されていないのでよくわかりません。
そういう事情もあって、まずはギリシア時代の哲学から始まります。
『ソクラテス以前哲学者断片集』
哲学というものは基本的にソクラテスから始まるとされます。しかしソクラテス以前にも哲学者はいましたし、またソクラテスではなくタレスを始めとする見解もあります。ソクラテスの孫弟子にあたるアリストテレスなどそうでした(はず)。
ソクラテスとそれ以前の哲学者の違いはなにか、といいますと、対象が異なると言われます。ソクラテス以前の哲学者は自然を哲学の対象にしました。それをソクラテスは人間に負けることにより自然の哲学から人間の哲学へと転換されたといいます。
そのためソクラテス以前の哲学者は自然哲学者なのですが、この態度は思いのほか現代の科学と強く結びついているようです。近代に入っても科学者はこうしたソクラテス以前の哲学者の学説をまとめて総合したアリストテレスの自然哲学の克服から今日のような科学の基礎を築いてきました。また自然を合理的に考える態度が極度に高く、その上古代の時点で高度に科学的な成果もあげていたのがギリシア哲学であり、その後ローマ時代のアレキサンドリア学派などでもあって、その原点としてソクラテス以前の哲学者は注目されます。
そう聞くとなんだか難しそうですが、この本の難しさはそれだけでなく別のところにもあります。というのもあまりに古い時代のものですので、著作が残っていません。そのためこの本はのちの時代に様々な著述家が引用したものを集めて作られたもので、それゆえに断片集と銘打たれているわけです。
しかもソクラテス以前の哲学者はかなりの人数がおり、それぞれ断片のみがまとめられているわけで読むのも大変ならなに言ってんのかわかるのも大変です。そのため巻数も多く難しい哲学書となっているのでした。
私はこの本は残念ながら読んでいませんが、他の断片集は何冊か読んだことがあります。網羅的な集成は多分この本になるかと思います。
プラトン『国家』
哲学はソクラテスから始まりましたが、ソクラテスはなにも書きませんでした。代わりに弟子のプラトンがその言葉と立ち振る舞いを記録し対話篇としましたが、後期の作品はプラトン自身の思想を述べたものだと言われます。
そのプラトンの中で難しいものとしてあげてみたのがこの本です。この本は題名通りの国家論でもあるので哲学書とは違うように思われるかもしれません。
しかし人間が生きる以上は他人とも共に生きていくしか自然環境の脅威から逃れるすべはありませんし(特に古代ですし)、しかしそうした集団が問題なく動いていくというわけでもありません。人々の集まる世界を考えることは人間を考えることでもあるのです。
特にプラトンは若い頃に師であるソクラテスの裁判と死を体験しています。最も優れたギリシア・アテネでの民主制の中で最も賢人と思われたソクラテスが民意によって処刑されてしまう、その矛盾をプラトンは抱え込んで生きていったという側面もあったようです。
そのためプラトンは晩年にある僭主のもと理想的な国家を建設しようとして挫折しました。そのプランとでも言えるようなものがこの本かもしれません。
しかしこの哲学書の内容は現代からすると問題が多い、ともいえます。というのも様々なものが規制された窮屈な世界でもあるからです。
たとえば有名な哲学王の理念がありますが、歴史はあまりこの理念を実現させませんでした。また詩人を追放して文化を切り離しています(こういう言い方でいいかはわからないけど…)。そのため全体主義の起源みたいに扱う人もいました。
ただこういう主張は現代でも同じように出てきますし、かといって世の中の問題を解決しようとすると似たことを考えてしまうかもしれません。
そのため様々な問題が絡みあって、そのうえ私達自身の問題とも交差するような問題を考えているためますます難しくなっていくのでした。
アリストテレス『形而上学』
プラトンの本は対話篇という形式で書かれていて、哲学書としては読みやすいです。そのため林達夫などはプラトンはまず文学として読まれるべきだ、という意見に賛成している人もいます。
しかしそれがアリストテレスになると途端に変わってしまいます。いわゆる哲学書としてイメージされる、大変難解でなにを書いてあるのか一行もわからなくなるような難しいものへと変貌してしまいます。
これには一応わけがありまして、プラトンは対話篇を自ら刊行した作品として書きました。そしてそれが残っているわけです。一方アリストテレスも師と同じようにたくさん対話篇を書いたらしいのですがすべて散逸してしまいました。
ではなにが残っているのかというと、アリストテレス自身の学校リュケイオンで行った講義の講義録が残されているとされます。そしてそれは未整理であったそうです(ちなみにプラトンは対話篇だけが残ってプラトンの学園であったアカデメイアでした講義録は失われたと考えられているそうです)。
その中でもこの『形而上学』は編集が混乱しているらしく、本文の中に急に哲学用語辞典のようなものが挟まれていたりします。そうした事情もあるうえで、アリストテレスの哲学が殊更難解でますますわからなくなってしまう始末です。
ある意味ではアリストテレスによって哲学というものは初めて整理されたともいえるらしいので、この本は哲学が生まれて立ち上がろうとしているような素振りもあるのかもしれません。そのようなわけで大変難しい哲学書となっているのでした。
ローマ 5冊

ギリシア時代の哲学は長い目で見ればタレスから始まってアリストテレスで終わったといえるかもしれませんが、ギリシア哲学はそのままローマ時代の哲学へと流れ込んでいきます。ではなぜギリシアではなくローマなのかといえば、ローマ人が当時の世界支配を成し遂げてギリシアも傘下においたからです。
そのためローマが支配した時代の哲学として、ローマ時代のものとして次にむかいたいと思います。
プリニウス『博物誌』
プリニウスの『博物誌』は哲学書ではありませんしプリニウスも哲学者ではないのですが、あまりの大著で様々なネタ元ともなっている面白い本ですのであげておきたいと思います。
プリニウスの『博物誌』は題名にもあるように博物誌です。博物誌ってなんなのか、というとちょっと説明しにくいのですけれど、自然世界の諸々を集めて記述したものでしょうか。具体的には動物や植物、鉱物などの目録のようなものです。ここから近代に入って生物学や動物学、植物学、鉱物学などになっていくそうです。その最初期のとても大きな成果がこの本ですね。
この本ではプリニウスが様々な書籍から集めた情報を集めてまとめあげた、当時の百科事典のようなものにもなっています。宇宙から始まり地理や都市、動植物に人間、病気、鉱物や宝石といったものが順番に説明されています。
内容の記述は別に難しくなく、むしろ楽しくて面白いくらいです。プリニウスは眉唾物の伝説みたいな話もそのまま書いていて、マンドラゴラを引っこ抜くと叫び声を上げて死ぬから犬に引かせるとか、地上には頭のない人間がいるとか、ファンタジーものの創作に出てきそうな情報の宝庫です。
ではなにが難しいかというと、その長さです。翻訳にして上下に段組みで3分冊、計1500ページという大著です。しばらく前に普及版として再び世に出ましたが、一段組で6分冊になっています。
そのため中々通読するのは骨が折れます。ぺらぺらめくって楽しむのはいいのですが、全て読もうとなるととても大変です。そのため今回難しい本の一冊として含めてみました。
『初期ストア派断片集』
ギリシア哲学というものをプラトンとアリストテレスに代表させることは難しいことではありません。それどころか西洋思想そのものをプラトンかアリストテレスかのどちらかとみなすことも出来ます。そして2人とも自分の学校を持っていました。アカデメイア(プラトン)とリュケイオン(アリストテレス)といいます。
それぞれの学校は各々に発展していったそうなのですが、それとは別に新しい哲学の学派も生まれてきます。ソクラテス以前にも多士済々の哲学者、哲学学派がいたのと同じですね。
そしてその中でもローマ時代の最も代表的な哲学学派がストア派と呼ばれるものです。その中でもこの『初期ストア派断片集』は、題名通り最初の頃のストア派の哲学者の書いたものの断片を集めたものです。
ストア派の中にはちゃんと著作が残されている人もいるのですが、どういうわけか読みやすくて面白いという特徴があります。そのため難しいものとしてこちらをあげてみました。
断片集というように、『ソクラテス以前哲学者断片集』と同じで基となる本は散逸してしまったらしく、後世引用されたりしたものを集めたもののようです。そのため同じように読みにくくわかりにくいし、また巻数も多く含まれる哲学者の数もたくさんいるということになります。
残念ながらこちらは私は読んでいないので詳しくは説明出来ません。
セクストス・エンペイリコス『学者たちへの論駁』
ローマ時代の中心的な哲学のひとつに懐疑主義というものがあります。これはありとあらゆることを疑うことによって、真理を宙ぶらりんにしてしまうようなものです。特定の真理に従って固定観念に陥るのではなく、あらゆる真理から中立を保って平静(アタラクシア)をてにいれるという、そういうようなものです。
これはピュロンという人が始めた哲学の学派なのですが、ピュロンの本は残っておらず学派としても衰退しました。そしてだいぶのちにセクストス・エンペイリコスが復興して懐疑主義を後世まで残すこととなりました。
そして懐疑主義の哲学として独特の難しさがあるのは、他の学派に対する徹底的な批判にあります。プラトン派(アカデメイア)、アリストテレス派(逍遙学派)、ストア派、エピクロス学派(原子論)と軒並み批判の俎上にあげます。そのうえすべての学派に対してどれも間違っていることをあげつらっていくのです。
これが3巻分にわたって繰り広げられるのですが、問題はこの批判している他の学派の内容です。セクストスは当然当時存在していた各学派を踏まえたうえで批判しているのですが、そのほとんどが現在では散逸してしまいました。それどころかセクストスの本でしか当時の学派の様子を知ることが出来ないところもあると解説に書いてあったかと思います。
そのため現代の読者としての私たちは、その背景がどうなっているのかほとんどわからないままに多数の学派批判を読まなくてはいけません。そして懐疑主義はその性格上、自分たちの正しい真理というようなものを理論的に打ち立てたりもしません(多分。間違ってたらごめんなさい)。しかも懐疑主義の立場を述べたものには『ピュロン主義哲学の概要』というものがあり、『学者たちへの論駁』はその詳細な対立学派への批判ともなっており、いきなり読むにはかなりややこしいものとなっています。
ですがこの時代の哲学の考え方を知るには面白い本かと思います(よくわからないけど…)。
プロティノス『エネアデス』
(4巻が出てこなかった…)
ローマ時代には色々と哲学の学派が現れたのですが、ギリシア時代にあったプラトンやアリストテレスの哲学は学派が続いている内に色々と変わっていったそうです。後期のアカデメイアではピュロン主義とは違う形で、反ストア派のような懐疑主義に陥ったともいいます。プラトンの哲学はプラトンの学園ではちょっと変わってしまったのかもしれません。
それとは別にプロティノスという人はプラトンの哲学を自分流に受け継いで発展させました。そのためプロティノスの興した哲学の学派は新プラトン主義と呼ばれています。
その新プラトン主義のプロティノスの本が『エネアデス』なのですが、困ったことに完訳はプロティノスの全集にしか入っていないようです。そしてこれが高い! 巻数もそこそこありますが、まず手に入れるのが大変です。そのためこの本は内容如何ではなく全部読もうと思うと別の形で大変な哲学書です(そんなわけで私も残念ながら読んでません。まぁ図書館で探せばいいんですけど…)。
抄録されたものは中公クラシックスから出ていますし、その基となった『世界の名著』には他の新プラトン主義の哲学者の翻訳もあわせて収録されています。ですがこちらも結構高くなっています。新プラトン主義は中世以降のヨーロッパ思想史ではとても重要なのですが、多分直接はさほど今日と関係ないためか、あまり流行ってないのかもしれません。全集なんて田中美知太郎がやってるのに…
『ナグ・ハマディ文書』
これはキリスト教異端の文書で、古代にいれるべきなのか中世にいれるべきなのかちょっと迷いました。中世は間違いなく哲学より神学=キリスト教の世界ですが、まだこの文書が書かれた頃はそこまでいかず古代の範疇かと思いますので古代にしました。
キリスト教が成立して間もない頃、様々な異端が生まれたそうです。そのひとつがグノーシス主義というもので、それがこの文書の内容です。
古代キリスト教では救済の問題をどう考えるかという点でかなり色々な対立があったようです。グノーシス主義というのはこの世界は誤った神によって作られたもので肉体的なものであり、真の神が作った精神的なものによって超えて真の神の世界へ行こう、というようなものです(間違ってたらごめんなさい)。旧約聖書の神が誤った神で、新約聖書の神が真の神として聖書を読み替え、真の認識=グノーシスによって乗り換える、ちょっと仏教の解脱みたいなキリスト教です(違うかな)。
他にもペラギウス派というのもあり、これは神の恩寵とは別に人間の力を信じて乗り越えていけるというものです。これも異端となりました。では正統はなにかというと恩寵論というもので、人間はどこまでいっても原罪につきまとわれた存在で、神の恩寵をもってしかどうすることも出来ない、というようなものです。アウグスティヌスの立場はこれで、ペラギウス派やグノーシス主義を批判し戦いました。
考えてみると面白いのですが、グノーシス主義は知恵によって乗り越え、ペラギウス派は人間の力を信じて乗り越え、恩寵論は人間は駄目で神の恩寵のみにより救われる、というわけで、現代的な観点からすると正統思想の恩寵論の方がおかしくみえます。しかしこれは私たちたが現代人だからで、宗教批判のうえにたつ文化で生きているからでしょう。
しかしもうちょっと考えてみると、この思想的な対立は今でも似たようなところがあります。人間は自分の努力だけでなんでも出来るのか、といえば、そうではありません。しかし教育的メッセージは努力を盛んにいいます。ですがなにもかもらうまくいかなければ心に支えを求めないといけないかもしれません。またうまくいくためにはその方法や失敗の原因を見つけなければなりませんが、それは知恵によってしか出来ません。意外と同じ関係があり、古代でも現代でも問題の内容は変わらないのかもしれません。
まぁそれはともかく、この本がなぜ難しいのかというと、発見されたの20世紀中頃でつい最近といっていいくらいのもので、しかも古代のものですから状態がいいわけもなく文書自体がかなり壊れているからです。そのため読んでもひとつひとつの文章自体がろくに読めないというものになっています。
翻訳を開くとそこかしこに空白の行が存在し、何字空く、というようなことが頻繁にあります。また同じような内容でも文書自体が壊れているため並列して記載されていたりして、普通の本とかなり体裁が違います。こうした点に慣れても、古代キリスト教異端説の内容は簡単ではなく、またその文書はキリスト教だけに限らず非キリスト教グノーシス主義というものも含まれているらしく簡単にはいきません。
ですがグノーシス主義はひと昔かふた昔前くらいの漫画、アニメによく使われていた印象がありますので(エヴァンゲリオンの影響かな)、興味を持つ方は読んでみると面白いかと思います。
追記:岩波文庫から抄録が出ました。
中世 4選

中世となると純粋な哲学はなりをひそめて神学が中心になります。それはキリスト教において真理は聖書の中にあるのであって、理性=哲学の中には真の理解はないからです。キリスト教=神学が真の真理であり、哲学の真理は二流の真理なのです。そのため純粋な哲学はいなくなって神学ばかりになりました。
しかし神学といっても聖書は理論的な書物ではありませんので、理論的な説明部分を敵であるギリシア思想から借りて説明しだしました。そのうちキリスト教は哲学を借りて神学を作りあげるようになり、神学の中に哲学の重要問題が含まれるようになりました(多分。そう間違ってない説明だと思うけど…)。
そのようなわけで、中世の哲学は神学になります。ギリシア・ローマ文化/思想の正統後継者はイスラームへと移りましたが、残念ながらここではそこまでは紹介できません。
『中世思想原典集成』
(20巻が出てこない…)
中世の哲学/神学といっても、そんなにうまく選べません。私が知らないだけかもしれませんが、あまり中世哲学の古典というものは翻訳されていないようです。あるにはあるのですが、むしろキリスト教としてのものであり、哲学としてのものは多くはないらしいです(違ってたら申し訳ない)。
そんな中で中世の思想を、古代から近世まで含めた射程で、宗教としてだけでなく哲学としての側面を強く打ち出したものとしてこのシリーズがあります。
20巻にも渡るこのシリーズは古代の初期キリスト教思想家から近世のスコラ学者までを集めたアンソロジーです。対象範囲が膨大に広いため抄訳されたものがかなり多いです。しかし短いものは完訳されていますし、抄訳でも非常に重要なものがたくさんあるかと思います。
またそうした性格上ここでしか日本語で読めないものもたくさんあります。しかも中世哲学のビッグネームにあたる人たちのものもたくさんあります。さらに各巻巻頭だけでなく各々の作品の前にも各解説があり、とても参考になります。
ですがそのために読むのはものすごく大変です。なにせ各巻1000ページ近くあるものが20冊もあるのです。死んでしまいそうです(天国に召されるかも…)。中世哲学の一望が一挙に流れてくるような感じです。質量共に難しい代表格かもしれません。
最近になってさらに抄録されたライブラリー版が出ました。こちらは7冊です。ですが当然かなり収録作が減っていますので、全部読みたい人はもとの版を手に取った方がいいかもしれません。でもそこまでしなくてもいいと思われる方は、おそらくライブラリー版のほうがいいかもしれません。大変すぎるから…
さらにまた新しく第二期なんて出ました。すごい!
アウグスティヌス『神の国』
アウグスティヌスは初期のキリスト教を思想的に大きく支えた大哲学者です。
アウグスティヌスは新プラトン主義の哲学をキリスト教に結びつけて後々まで大きな影響を与えたとても偉い人です。若い頃放蕩の暮らしをしていたそうですが、改心してキリスト教に入信しました。キリスト教入信以前にはマニ教にも熱心だったそうです。そのためもあるのか初期キリスト教異端説やマニ教に対して論戦を繰り広げもしたそうです。
この本は岩波文庫で5分冊もある大著です。私は他の本は読んだことありますが、これは読んだことありません。ただ長いので『告白』ではなくこちらを選ぶことにしました。
トマス・アクィナス『神学大全』
から
古代の哲学が極端なことをいえばプラトンとアリストテレスであったとすれば、中世の哲学を極端にいえばアウグスティヌスとトマス・アクィナスになるかと思います。あまり中世の哲学に対して記述の多くない哲学史の場合、この2人が代表のようにして出ていることもあったかと思います。
そしてアウグスティヌスがプラトンだとすれば、トマス・アクィナスはアリストテレスです。中世の中頃になってヨーロッパにはアリストテレスが再度入ってくることになって、トマス・アクィナスによって大成されました。それがこの本です。
ヨーロッパはローマ帝国の崩壊と共にギリシア文化も失われました。その継承はアラビア世界に移るのですが、その後アラビアからヨーロッパに輸入されていきます。その後アリストテレスに対する反発と受容が起こるのですが、トマス・アクィナスが書いた頃にはまだ反発があったようで、トマス・アクィナスがキリスト教の正当思想となるには時間もかかったようです。
この本は難しいのもそうなんですが、とにかく膨大な量で、翻訳で40冊近くあります。その上出版していた創文社が廃業してしまいました。手に入れるのも置いておくのも読むのも大変な本です。もちろん私は読んでいません。ちなみに世界の名著の中に抄訳されたものもあります。
オッカム『『大論理学』注解』
(4と5が出てこない…)
オッカムは中世後期のいわゆるスコラ哲学者になるのですが、残念ながらあまり知りません。オッカムの剃刀が有名です。ただ中世がちょっと少ないので大著があるものですから載せてみました。
中世の本というものは、あまり独立した著作としては現れないそうです。過去の権威に結びつけて書いてしまったりして、そのため偽書と呼ばれるものが多いみたいです。たとえば中世に描かれたのに古代のアリストテレスの書いたものとして書かれたものなどがあり、そうしたものは偽アリストテレスと呼ばれたりします。
それとは別に権威ある書の注釈として書かれるものも多かったそうです。しかしそれは注釈といってもただの解説書ではなく、過去の権威ある書を借りながらその中で注釈の形をとって独創的な思想を書くことも多かったといいます。おそらくオッカムのこの本もそうした中の一冊かと思います(違っていたらごめんなさい)。
近世/近代 10選

哲学の本番は近世/近代に入ってからで、ここからがいわゆる哲学として難しい本が出てくるイメージになるかと思います。今回は近世と近代をいっしょくちゃにしてしまいましたが、どのあたりで明確に区切ればいいのかわからないのでそうしました。漠然としたイメージではデカルトからヘーゲルぐらいまでを浮かべています。私の能力の限界もあってこのあたりいいかげんですがおゆるしください。
キリスト教 2冊
このあたりは近世なのか中世後期なのか私にはわかりかねるのですが、一応このあたりにおくことにしました。
ヤコブ・ベーメ『黎明』
ヤコブ・ベーメはキリスト教神秘主義の人なのですが、もともとは靴職人です。そのため他の思想家のように学問をやったわけではありません。それが関係するのかわかりませんが、とにかく説明が難しくてよくわからない気がします。翻訳も古いものしかないのでそれも合わさってか大変難しいです。
もともと神秘主義だから合理的に説明できるものではないのですが、しかし同じ神秘主義でもエックハルトなどは読みやすいです。むしろ読みやすすぎる感じがあり、西洋の中の東洋思想みたいな印象を受けます。それに対してベーメはもっと違う何かのような気がするのですが、残念ながら私にはわかりません。ぜひ興味のある方は読んでみて内容をつかみとってみてください。
後で気づいたのですが、こちらの叢書ではもっと新しい訳があるみたいです。
カルヴァン『キリスト教綱要』
カルヴァンはルターと並ぶプロテスタントの代表的な思想家です。そして体系的な神学書をプロテスタントの立場で初めて書いた人とも説明されていました。
そのためこの本はプロテスタントの神学者です。哲学とは異なるのですが、哲学とは違う立場と観点でひとつの壮大な体系を築いているという点で、哲学の側から見ても面白いかもしれません。
内容は私にはわかりかねるのですが、多分キリスト教の本質的な原理についての説明から、カトリックに対する様々な批判、論敵との論争の数々が述べられているようにも思えます。
そのため批判しているカトリックの制度や教義、論敵の思想内容など事情を知らないと非常にわかりにくいということがあるかと思います。そのあたりセクストス・エンペイリコスと似た難しさがあるかもしれません。
また私が知っている旧版は左右二段組で各巻300ページ前後の計6冊という大著です。なんとなく一冊一冊が薄く見えたので気楽そうな気がしたのですが、まったくそんなことはありませんでした。その点でも難しい本の中に『キリスト教綱要』を入れてみました。
それと思想的土台はどうやらアウグスティヌスのようであちこちで引用・参照されています、
哲学 8冊
デカルト『省察』
近世/近代哲学の始まりはデカルトにあるといわれます。デカルトといえば〝我思う、故に我あり〟で『方法序説』です。しかし『方法序説』は短い本ですし、どちらかといえば読みやすい方です。
そこで『方法序説』の哲学的な続編ともいえる『省察』を難しい本の一冊としてあげてみました。けれども『省察』もそう分厚い本ではありません。しかし白水社から出ている『デカルト著作集』に入っている『省察』はそんなことありません。
なぜでしょうか。他の文庫本などで出ている『省察』と何がちがうのでしょうか。それは『デカルト著作集』版は『省察』だけでなく、原本にもあった質疑応答の書簡も含めて翻訳され収録れているからです。
そのため文量は爆発的に増えました。『デカルト著作集』4分冊のうち一冊丸々が『省察』になっています。そしてその手紙でのやりとりも難解な哲学の内容に深く踏み入ってやりとりされたものであり、大変難しいです。そのうえ中には手紙や相手が哲学史上に名を残したホッブズやガッサンディという哲学者までいます(ただデカルトはホッブズを評価していなかったらしく簡単に済ましています)。
なんでもデカルトの書簡というものは当時の主要な学者・知識人との交流を含み、内容は高度で手紙自体が一編の論文に値するそうです。当時は学術雑誌などなかったのでその役割を手紙が果たしたとのことです。それだけでなくこの時代の社会史・文化史としても貴重な記録であり、その資料価値は時にデカルト自身の著作以上にある、なんてことも解説に書いてあったかと思います。そしてデカルトの書簡集も翻訳されています。
また『デカルト著作集』の『省察』の翻訳はなんでも非常に学問的なものらしく(Amazonレビューに書いてあった)、デカルトの一語一語に日本語を対応させた名訳らしいのですが、なんだか大変読みにくい気がします。研究心などないただの一般読者にはその翻訳の価値がわからず、大変難しく思えたことも『省察』を難しい本の一冊に数えてみた理由でもあります。気になったら一度読んでみてね。
ホッブズ『リヴァイアサン』
ホッブズは政治哲学の開祖です。ホッブズ自身その自覚があったらしく、私によって初めて政治哲学が始められた、と述べたそうです(政治学史の本で読んだ)。そのためもあってか『リヴァイアサン』は理論的には非の打ちどころのない完璧な理論なのだそうです。
『リヴァイアサン』の内容はよく言われるように、人間は自然状態に放っておくと万人が万人の狼であり互いに食い合うので、より巨大な化け物(=リヴァイアサン=国家)であっても大きな力で制御するべきだ、というわけで国家の正統性を証明した、というものだと思います(大体はあってると思うけど、間違っていたら申し訳ありません)。
しかし読み始めてみると最初の方は延々人間についての理論的考察が行われ、終わりの方になると延々聖書について述べられていて、一般的なイメージだけですまないような哲学書です。そのうえ岩波文庫だと4分冊で、中々簡単には読み終わりません。ですが今日まで続く国家というものの最初の理論のひとつなので、大変重要な古典であることは間違いないかと思います。
ロック『人間知性論』
ロックはイギリス経験論の祖といわれています。経験論というのは簡単にいえば、人間の頭に浮かんでくるものは生まれつきあるわけではなく、外から(=経験)得てくるものだ、ということになるでしょうか(間違ってたらごめんなさい)。
そんなイギリス経験論の始まりである『人間知性論』ですが、これまた岩波文庫で4分冊の大著です。しかも認識論であり純粋に哲学的なテーマでもあって簡単には読み通せない本でもあります。しかし人間の認識とはどのようになっているのか、ということを思弁的に哲学として説明されているので、もし似たような問題を感じている人がいれば非常に役に立つかもしれません。
ロックは哲学者なのですがお医者さんでもあり政治家でもあって、著作も多岐にわたっています。その中でも哲学者としての主著は文句なく『人間知性論』であり、中心的な書物になるのでロックの他の著作との中でも最も重要なものになるかと思います。
ヒューム『人性論』/『人間本性論』
ロックがイギリス経験論の創始者であるとしたらヒュームはイギリス経験論の完成者と言われます。ヒュームは徹底した懐疑の立場をとったそうです。ただ私にはヒュームが難しすぎてあまりよくわかりません。
『人性論』は岩波文庫で出ていましたが、法政大学出版局から『人間本性論』の題名で新しい訳で出ました。文庫版は4分冊、単行本は3分冊となっています。長さもなかなかのものです(ただロックよりかは一冊一冊が薄い)。
全体の構成としては3部に分かれていてそれぞれ知性、情念、道徳となっています。内容はちゃんとお伝えできる自信がありませんので関心がありましたら直接お読みください。
ただ情念論の部分で様々な感情を分析していって定義しているあたりが、あまり他にはなさそうな気がしました。哲学は理性を尊ぶので感情を扱うのは珍しいのかもしれません(そんなことなかったら申し訳ない。そういえばショーペンハウアーも感情について書いてたような気がするな…)。
スピノザ『エチカ』
スピノザはユダヤ人なんですが、ユダヤ社会から破門されたり、オランダに亡命してレンズ磨きをしていたりと逸話の多い人です。思想としては汎神論というもので、世界の隅々まで神さまが行き渡っている、とでも言えばいいのでしょうか(いや、間違ってるかもしれない)…
あまり内容に関しては自信がないのでこちらも直接読んでもらえれば嬉しいのですが、『エチカ』の難しさは内容だけではありません。記述形式自体が難しいのです。
普通、本というものはこのように文章にして順番に説明していくものですが、スピノザは『エチカ』においてそのような方法を取りませんでした。そうではなく、当時最も厳密な真理の記述方法と思われたユークリッドの幾何学の方法を使って、それぞれの哲学的命題を証明していくという方法をとりました。
そのため一般的な哲学書どころか、普通の本を読んでいても慣れない形式で哲学が進んでいきます。このあたりが『エチカ』の難しいところではないかと思います。
岩波文庫だと上下巻で2冊しかなく短いのですが、長さでは測れない難しさが『エチカ』にはあるのでした。
なんとスピノザの全集まで出ました。
カント『純粋理性批判』
カントは近代哲学の神髄です。そして哲学書の中で難しいものの最高峰のひとつでもあります。どこで言われていたか忘れましたが、哲学三大難解本としてカント『純粋理性批判』、フィヒテ『全知識学の基礎』、ヘーゲル『精神現象学』があげられていた覚えがあります。そのためここからが最難解な哲学書の本丸であるとも言えるかもしれません(ネットで検索したらフィヒテではなくハイデガーとなっておりました。私の勘違いかもしれませんが、なんとなくフィヒテと読んだ覚えがありましたのでフィヒテと載せてしまいました。間違ってたらごめんなさい)。
追記:岩波文庫『全知識学の基礎』を読み直していましたら、訳者の序文にフィヒテを三大難書と述べている箇所がありました。私はこれを覚えていて上のように書いたようです。古い翻訳なので昔はフィヒテを三大難解本とみなしていて、いまはハイデガーが三大難解本になったのかもしれませんね(わからないけど)。
カントの『純粋理性批判』はロックの『人間悟性論』から始まった近代認識論の総決算です。人間がいかに物事を認識し考えるのかということが非常に綿密かつ緻密に説明されています。恐らく『純粋理性批判』一冊を十分に理解することが出来れば哲学というものに対しても大きく理解を持つことが出来るでしょう(私? 私は無理無理…)。
しかしそれゆえにカントは大変難しいです。なんといいますか、当たり前の常識と思われるものが全部一旦引き剥がされたうえで、もう一度再構成して人間の認識の在り方を説明されている、といった感じでしょうか。私たちにとって日常的に当たり前だと思っていることが一から説明されていくことによって大きく揺らいでいく、そんな感覚に襲われる気がします。
また認識の在り方が説明されると同時に認識の限界も線引きされることにもなります。いわゆる4つのアンチノミーですが、これによって人間の理性が論理だけでは真理に到達することが出来ないことが示され、経験的なものによる後ろ盾のある領域のみに理性の利用を制限されることによって科学を哲学の側から基礎づけることにもなりました。
文量もとても多く、大体文庫本だと3分冊前後です。もっと多いものもあります。数ある難解な哲学書のうち、なにがなんでも最終的に読まなければならないのはカントかもしれません。
フィヒテ『全知識学の基礎』
フィヒテはカントの後を継ぐような哲学者ですが、最初カントには熱心に受け入れられながら、あとになって自分の哲学とは違うとみなされるようにもなりました。
フィヒテも難しいのですが、多分カントやヘーゲルの方が難しいと思います。岩波文庫だと上下巻で、比較的短い本です。
フィヒテはカントの後の哲学者ですが、ヘーゲルの前の哲学者でもあります。というのも有名な弁証法はフィヒテの手によるものだからです。
この弁証法が難しくて私にはわからないのですが、フィヒテは自我と非我をたて、非我から自我へと取り込むような形で認識を得ていくようなイメージなのでしょうか(全然違うかもしれない)。…自信ありません。説明するのやめておきます。関心ありましたら読んでみてください。
ヘーゲル『精神現象学』
ヘーゲルは難解な哲学書の中でも特別に難しい哲学書で、難解本の王様のような哲学者です。私なんかさっばりわかりません。
ただ『精神現象学』はカントが『純粋理性批判』で認識の限界を区切ったように思えたものを、弁証法を使ってそんなもん関係あるかと突き抜けたような印象の哲学です。かつては神の僕であった人間や哲学が、自分たちこそどこまででも行ける、というような感じでしょうか。素朴な感覚的な認識から絶対知にまで至る精神の展開を説明しています(多分。そんなに間違ってないと思うけど…)。
そんな内容だけでも難しいのですが、元のドイツ語でも難しいという『精神現象学』をそのまま難しさまで忠実に訳したというのが岩波全集版の『精神の現象学』です(訳者の理解によりちょっとタイトルが違います)。
これが大変です。本文でも無茶苦茶長いのに、それ以上の注がついていたりします。つまり他の翻訳に比べてほとんど分量が倍になっているような翻訳です。1ページ読むのに注を何ページも読まなくちゃいけないような本です。
しかしそれゆえに注釈は詳細で『精神現象学』読むならこれだ、という人もいます(私はやめた方がいいと思いますけど)。そのため最難解本としては岩波全集版こそがふさわしいかと思い載せてみました。
ちなみに『精神現象学』は最近文庫等で新訳も多く出ているので、他の翻訳から読むことも大変ではありません。同じことはカントの『純粋理性批判』にも言えるかと思います。
ヘーゲル以降 8選
ヘーゲル以降というのは他の時代区分と比べて変な気がするのですが、ヘーゲル以降を近代とするわけにもいきませんし、現代とするには現代思想というものもありますから適当ではないような気がしました。そこで座りが悪いですが、こんな標題となりました。
ただ確かにヘーゲル以降によって哲学は変わったようにも見えますし、哲学が哲学だけで済まなくなった、もしくは哲学の役割が無くなってきつつある、というようなことはあるかもしれませんので、それなりに丸っ切り見当違いということでもない、と思っておくことにします。
フォイエルバッハ『キリスト教の本質』
ヘーゲルの哲学は当時のすべてを包み込むような大体系としてありましたが、ヘーゲルの死後に学派としては分裂したそうです。その後それぞれ左派、右派、中道派として分かれていったそうなのですが、そうしたヘーゲル学派分裂後の哲学者のひとりがフォイエルバッハです。
フォイエルバッハはかわいそうなことにヘーゲルとマルクスの間にある哲学者とか、ふたりをつなぐ哲学者とか言われているのですが、それだけで済まされるような哲学者なのかどうかは私には判断できません。
この『キリスト教の本質』はキリスト教/宗教批判の書としても有名ですが、とても簡単に単純化して言えば、キリスト教の神とは人間の理想像を投影した存在である、ということになるでしょうか(間違っていたら申し訳ない)。
神は人間の理想像の姿であるから、人間はいくら憧れてもその存在にはなれず、卑小な人間として神から疎外されている、という観点から、のちのマルクスの考えへともつながっていくようです(難しくてよくわかってないから上手く説明できないけど)。
これはなんとなくわかりやすい考え方のような気もしますね。私たちのようなキリスト教徒ではない人間からすると、神さまは人間の理想像である、ということはそんな気がしてきます。ただキリスト教が本当にそれくらいの説明で済ませられるのかは、これもわかりません。多分それでは済まない気がしますが、それは他の神学の本を読むことで理解が深まっていくかもしれません。神学も読むと漠然として理解したつもりになっている宗教の姿とは全然違います。
むしろこうした哲学の側による宗教の批判後の世界に生きているためそう思うかもしれませんし、またその点『キリスト教の本質』は読みやすいかもしれません。ただ岩波文庫では上下巻ですが各巻がとても分厚いです。読むのは相当大変な哲学書かと思います。
マルクス『資本論』
マルクスが、しかも『資本論』がなぜ哲学書なんだ、と思われるかもしれませんが、ヘーゲルとの関係で載せることにしました。
どこかで読んだ覚えがあるのですが、『資本論』は『精神現象学』に対する最も詳細な注釈である、というようなことが書いてあった気がして、私にはまったくその意味がわかりませんが難しいことに関してはどちらも双璧だろうと思われますし、ヘーゲルとのそうした関係があれば哲学との関係も皆無ではないだろう、と一応考えてみました。
マルクスはもともとヘーゲル学徒だったのですが、ヘーゲルを継承すると同時に批判もしました。そのひとつに哲学者はこれまで世界を解釈することばかりをしてきたが、これからは世界を変えることが役割である、というようなものがあります。
これは結構重要なことで、古代ギリシア哲学においてもアリストテレスは観照的生活を至上のものとしましたが、プラトンは自分で政治をやる意思を持ち続けていました。この対立が近代でも同じように現れてきた、と見えないこともありません(違ったらごめんなさい)。ただ古代においては実践的生活(プラトン)より観照的生活(アリストテレス)の方が後に来たのですが、近代では観照的生活(ヘーゲル)の後に実践的生活(マルクス)が来たことになります。そのためかどうかわかりませんが、書斎に閉じこもる知識人より社会に出る行動派の方が偉いようなイメージを持っているかもしれません。政治関係者でもそう思っているらしく、学者や知識人を馬鹿にした口をきく人もいます(しかしそういう人がマルクス主義者かといえば真逆だったりします)。
ともかくヘーゲルによって認識世界が総体的に築き上げられてしまったとして、その後にすることはなにか、という問題として、こうした実践活動に向かうことはひとつの当然の選択かとも思います。共産主義は失敗したかもしれませんが、こうした態度決定は思想の左右を問わずに現れてくるかと思います。その意味で古代も近代も政治と思想に関しては同じ問題を抱えているのかもしれませんね。
その現代版でもあり最も影響のあったマルクスを読んでみるのも面白いかもしれません。
ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』
(1が出てこない…)
ショーペンハウアーはヘーゲルの同時代人であり、ヘーゲルと同じ時間に講義して対抗しようとしたけど学生は全員ヘーゲルの講義に出て誰も来なかった、なんて逸話もある人です。
ですからヘーゲル以降というのは時代的に合わないのですが、思想的にはヘーゲル以降といっていい影響の仕方をしているかと思いますのでここにしてみました。
ショーペンハウアーは一般的に実存主義の祖のようにも言われています。そしてニーチェもショーペンハウアーから影響を受けていたはずなので、これは間違いではないかと思います。しかしショーペンハウアー自身は先生からプラトンとカントをマスターするまでは他の哲学書を読むな、と言われたくらいカント的な人だそうです。
『意志と表象としての世界』の翻訳は世界の名著に正編だけ訳されており、後編も含めては恐らく『ショーペンハウアー全集』の中にあるものだけしかないかと思います。正編にしても上下二段組で500ページほどと大著です。
ショーペンハウアーは若い頃に主著である『意志と表象としての世界』を書き上げ、あとは細かいものを書いただけで早熟の哲学者であったかもしれません。母はゲーテのパトロン集団のひとりだったらしく、少年の頃ショーペンハウアーはゲーテに才能を太鼓判押されたとか、そういう逸話も多い人です。
ニーチェ『ツァラトストラかく語りき』
ニーチェは特別分厚かったり難しすぎるというわけではないのですが、新潮文庫に入っている翻訳は格調高い名訳とされていて、その分ちょっと難しく感じるかもしれないので載せてみることにしました。
ニーチェの本はアフォリズムが多いので、むしろわかろうと思えば簡単にわかってしまう面があります。ほんの数行で書かれた箴言はひとつひとつは別に難しいものではありません。しかし著作を通して読んでいくと、すぐに相矛盾するような箴言にぶちあたります。するとニーチェの本当に言いたかったことはなんなのか、わからなくなってきます。
そのためニーチェは単独で読むよりも全体で読むことにおいて難しくなる哲学者かもしれません。その点『ツァラトストラかく語りき』は劇的な表現で一本通した作品となっているのでわかりやすいところもあるかもしれません。それを格調高い(けど難しく感じる)翻訳で読むのもいいかもしれませんね。
フッサール『イデーン』
フッサールは現象学という哲学を打ち立てた現代のとても偉い哲学者です。その現象学についてまとまった説明をしている哲学書のひとつが『イデーン』です。
戦前に岩波文庫から出ていたものもあるのですがそれが上下巻だったのに対し、みすず書房から出たものは全5巻となっています。また注もたくさんついてぱっと見だと同じ本の翻訳だと思えないくらいです。
内容については残念ながら私には十分説明出来る自信はありませんので出来ませんが、現象学はあちこち他の分野とも結びついて発展していきましたので、そうした原点としても読むと面白いかもしれません。
ハイデガー『存在と時間』
ハイデガーはフッサールの弟子です。ナチスに協力したと言われたり20世紀最大の哲学者と呼ばれたり色々な評価があります。
ハイデガーの『存在と時間』は人間の在り方そのものを問おうとした哲学書だと思うのですが、これまた難しくて私にはわかりません。大体文庫などで2〜3分冊で出ていることが多く、読むのが大変です。難しさも折り紙つきといっていいでしょう。
こちらも自信ないのでこれくらいにしておきます。
レヴィナス『全体性と無限』
レヴィナスもフッサールの弟子だったのですが、ハイデガーと違って自身もユダヤ人であったため大変酷い目にあいました。
その経験を踏まえてレヴィナスは倫理学を哲学の最重要課題と考え『全体性と無限』を書いたようです。それは他者論と呼ばれるそうですが、目の前にいる存在が自分と同じ人間であり無限の存在として在るということが顔から現れてくる、というようなものだった気がします(違うかもしれない。よかったら直接読んで確かめてみてください)。もしかしたら全体性というものが社会や世の中で、無限というものが他者である個人=人間ということかもしれません(随分昔に読んだのでうろ覚えで申し訳ありません)。
昔は分厚い単行本でしか出ていませんでしたが、最近は文庫でも出て手に取りやすくなりました。でも難しいことは変わりないと思いますけど、分厚そうな単行本の方を載せてみました。
ウィトゲンシュタイン『哲学探究』
ウィトゲンシュタインも20世紀最大の哲学者と呼ばれたりするのですが、19歳で最初の哲学書を第一次大戦の塹壕の中で書き上げたとか、師匠のラッセルがウィトゲンシュタインの才能を一目見て見抜いたがウィトゲンシュタインの言ってることが最後までわからなかったとか、男兄弟がたくさん自殺したとか、逸話も多く天才として有名です。
ウィトゲンシュタインは最初の本である『論理哲学論考』で哲学上の問題はすべて解かれた、と思って哲学をやめるのですが、思い直したのかまた舞い戻って哲学者になりました。そして後期の代表作とみなされているのが『哲学探究』です。
『哲学探究』は読んでてもちっともわからない、というか、読んでるこちらの頭の中を引き摺り回されるような哲学書かと思います。恐らく私たちが無意識に理解している規則はどこから来るのか、という問いを巡って思考しているのかと思うのですが、自覚できぬ問題を言葉を頼りにぐるぐる周遊しながら近寄っていこうとしているかのようです。
そんなわけで『哲学探究』はなにか答えや明確なイメージを与えてくれるというよりも、その問題と格闘する大変さや苦悩を伝えられるような、そんな読後感を持ってしまいます。大変難しいことは間違いない哲学書かと思います。
以上になりますが、説明があやふやさで不十分ですが、残念ながら私の限界として許していただきたいと思います。個々の詳しい内容はそれぞれの著作やその解説等により正しく理解していただけることを願っています。




































































![トマス・アクィナス 真理論 上 (中世思想原典集成[第Ⅱ期]001) トマス・アクィナス 真理論 上 (中世思想原典集成[第Ⅱ期]001)](https://m.media-amazon.com/images/I/51dBlfE8C4L._SL500_.jpg)
![トマス・アクィナス 真理論 下 (中世思想原典集成[第Ⅱ期]) トマス・アクィナス 真理論 下 (中世思想原典集成[第Ⅱ期])](https://m.media-amazon.com/images/I/51tbMXjDwbL._SL500_.jpg)
![アンセルムス著作集・書簡集 (3;3) (中世思想原典集成[第II期]) アンセルムス著作集・書簡集 (3;3) (中世思想原典集成[第II期])](https://m.media-amazon.com/images/I/51wIODL71gL._SL500_.jpg)