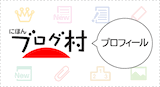前回のお話
本と読書と読める量
実存主義者ヤスパースと精神医学
ハイデガーの影響によって実存主義というものも出てきたそうなのですが(よく知らない。ちゃんと読んでない)、その中の1人であるヤスパースは最初哲学者ではありませんでした。じゃあなにをしていたのかというと、精神医学者だったそうです。
読まれないらしいヤスパースの大著
ヤスパースの書いた精神医学の本はとても大きなもので、日本では3分冊されて出版されています。私も読んでないのですが、どうやら世界的にもちゃんと読まれてないらしく、この本の一冊選集版みたいなものを出された本の序文で色々面白いことを書いてありました(そこだけ立ち読みした)。
【ヤスパース『精神病理学総論』】
(ヤスパースの本はこちら。私が立ち読みしたのは多分この最後のものだったかと思います。もし違っていたらごめんなさい)
というのも、この本はあまりに大著なので精神医学に関わる者は誰でも知っている。精神医学を志す者は最初の論文でこの本からの引用をすることが慣しのようになっているほどである。しかし精神医学の現場にいる医師も、どれくらいこの大著を読み通した者がいるかはわからない。恐らくほとんどの医師が全部を通読していないだろう。この本は読まれぬ大古典の一種である(だから読みやすくしたからエッセンスだけでも読んでね、というようなことだったかと思います)。

読むことが困難な多くの本たち
なんとなくこれはわからないでもありませんね。ただでさえ難しい本ですし、その上分厚くて3冊もあるとなれば専門家でも読み通すことは難しいということはあるのでしょう。たとえば『読んでない本について堂々と語る方法』なんて本も出てたりします。しかもこれはちゃんとしたフランスの批評家による本で、結構真面目な文芸批評の一種です(これは読んだ)。
【バイヤール『読んでない本について堂々と語る方法』】
また哲学や文学の世界でもすべてを読みつくすなんてことは不可能なので、読むべき本と読まずにすます本とをうまく判断することが読書のコツである、なんてことも半世紀くらい前から言われてたりもします。そうなると新しいものや手際の良い解説書に頼ってプロでも原典読んでなかったりするのかもしれません。

ここから、なんだ、専門家でもなんでも知ってるわけじゃないのか、と思ってもいいのですが、それより、専門家でもそうなら自分でも読むの足りてなくても落ち込むことないな、とか、いやいや、専門家でも読んでないならいっちょ読んでみるか、と大古典に挑戦してみてもいいかもしれませんね。
なんだか余談で終わってしまった回になってしまいました。
次回のお話
お話その290(No.0290)