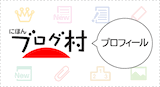前回のお話
中世の哲学とアリストテレスの微妙な関係 ~中世に知られていたアリストテレスはちょっとゆがんだ形で伝わっていた - 日々是〆〆吟味
中世におけるアリストテレス
アリストテレス哲学とトマス・アクィナス
アリストテレスはちょっとキリスト教と合わないところがあるのですが、論理学はアリストテレスによってある一つの型としては完成されていた面もありまして、そのため中世において最終的には大変支えともなったそうです。

それを成し遂げたのがトマス・アクィナスという中世最大の神学者なのですが、そのようなことがなぜできたのかといえば、アリストテレスの翻訳を新たにいちから揃えるような真似をしたからだそうです(確かそんなことを書いてあったような気が…)。
中世におけるアリストテレスの著作の状況
なんでも当時のアリストテレスの著作というものは版によってかなり違いがあったそうです。そのため現代の中世哲学の研究者はアリストテレスの全集を手元に置いておくだけではまったく用を為さず、中世に流布していたアリストテレスの著作集のそれぞれの版を揃えていなければならないと言います(解説に書いてあった)。
【宮下志朗『普遍論争』】
(この本にも書いてあったんじゃないかな…あまり記憶が確かではありません)
版違いで内容の異なるアリストテレス
というのもAという人とBという人が有力な思想家だとして、それぞれ依拠していたアリストテレスが内容において一致していないということが当たり前にあるそうです。そのためAの人が読んだアリストテレス著作集とBの人が読んだアリストテレス著作集がなければ、AとBという人の考えを研究出来ないというわけです。

イスラーム思想化されたアリストテレス
その上アリストテレスはイスラーム経由で入ってきました。そのためイスラームの思想家が自分たちの考えたようなアリストテレスへと変わっていってしまっているわけですね。まぁ和製英語とかナポリタンとかそんな感じなんでしょうか。そうするとヨーロッパに入ってきたアリストテレスのうち、どこまでがアリストテレス自身のものでどこからがイスラーム思想家のものなのかわからないわけですね。
トマス・アクィナスとアリストテレスの翻訳
またアリストテレスのものではないのにアリストテレスのものとされていた本もありました。こうした状況を踏まえてトマス・アクィナスは知り合いに頼んでアリストテレスをギリシア語原文からのラテン語訳を新しく作ってもらうことにしたそうです。そのうえで再度アリストテレス自身と取り組もうとしたのだそうです。
【中世思想原典集成『トマス・アクィナス』】
(この本の中にもこうしたこと書いてあったような気がします。こちらはこの集成の中の一冊で、トマス・アクィナスの小さなものが集められたものです)
トマス・アクィナスとアリストテレス偽書の気づき
またトマス・アクィナスは他のギリシア・ローマ哲学の本も読んでいたため、アリストテレスのものとされていた『原因論』がプロクロスの『神学要綱』であるということにも気づいたといいます。こうした努力や背景があって、ようやくトマス・アクィナスはアリストテレスを神学に組み込んで大成することが出来たわけですね。
【世界の名著『プロティノス,ポルピュリオス,プロクロス』】
(プロクロスはこちら。私も読んでみたい。あまり古本屋でも見かけない気がします)

そんなわけで、翻訳も馬鹿にしてはいけない、ということがここでもわかりますね。現代では輸入学者なんて呼ばれたりもしますが、これは結構重要な仕事であることがわかるお話でした。
次回のお話
プラトンのイデア論とキリスト教の結びつきと根源的思考の神への影響 - 日々是〆〆吟味
お話その260(No.0260)